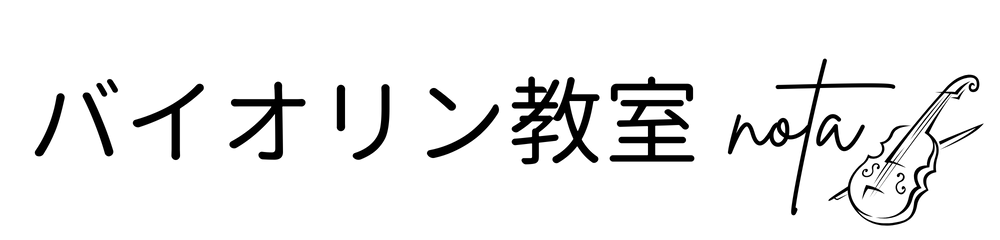新興写真とその時代に生きた音楽家たち
以前、この写真展を観に行きました。
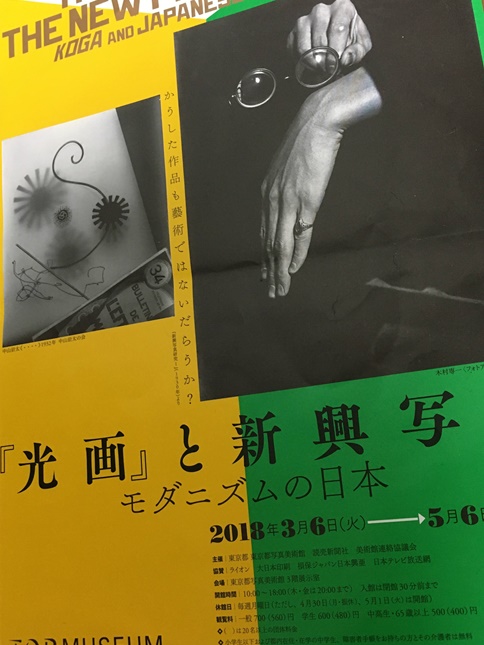
美術館に行くのは好きなのですが、メモしたりすることはないです。でもこの写真展は初めて鉛筆でメモをしました。
この写真展に行くきっかけとなったのは、大正時代のバイオリニスト、貴志康一の宣材写真です。とてもカッコよくて印象に残ったので、撮った写真家を調べたら、中山岩太という人物でした。

その中山岩太の写真がいくつか展示されるということで、東京都写真美術館へ。
写真のことは全くわからず、新興写真というものもわからず、展示室へ。そして、新興写真がどういうものなのかという説明文をメモしました。
新興写真とは、カメラやレンズによる機械性を生かし、写真でしかできない表現をめざした動向らしいのですが、その他に、
純粋な個人の芸術的表現と社会的ツール。
対象を客観的に正確に把握し、新しい美を発見して表現すべきこと。
これって音楽にも共通する言葉なのではないかと思います。特に二つ目の文章は私が苦手とすることだと思ったので、言葉で簡潔に表現されてのを見た時はすっきり?したような感じになりました。自分では言い表すことができなかったので。
実際に写真は、その人が感じた美を写し、本当に自由な感じがしましたが、自由の難しさも感じられる、複雑な作品が多く、強いメッセージを感じました。
好きな写真が多いなと思ったら、そういえば私、この時代の音楽家が好きなことにも気がつきました。この説明文が新興写真を撮っていた時代の音楽家にも当てはまるなと思いました。
例えば、プーランク、プロコフィエフ、レスピーギなど。
この時代を生き抜いた音楽作品は説得力があり、凄まじいエネルギーを感じます。
それだけ弾くのも大変な作品が多いです。
でも、この時代だけではなく、この二つの文章は、すべての芸術において当てはまるかもしれません。
久しぶりにマジメに書いてしまいました。
バイオリン講師 澤井亜衣